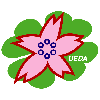第20回自主制作映画コンテスト 結果とコメント
うえだ城下町映画祭第20回自主制作映画コンテストは153作品の応募がありました。
審査員3名(大林千茱萸、柘植靖司、古厩智之)による審査の結果、ノミネート13作品が選出され、その中から大賞1作品、審査員賞3作品が決まりました。
また、全153作品を対象に実行委員会で行った審査で、実行委員会特別賞1作品も決定しました。
受賞作品
| 作品名 | 監督名 | 時間 |
|---|---|---|
| 大賞 『ジンジャーミルク』 |
今井ミカ | 59分17秒 |
| 審査員賞(大林千茱萸賞) | 鈴木竜也 | 22分 |
| 審査員賞(柘植靖司賞) 『僕らの存在を聴け』 |
白田悠太 | 56分 |
| 審査員賞(古厩智之賞) 『かぐやびより』 |
津村和比古 | 106分 |
| 実行委員会特別賞 『走れ!走れ走れメロス』 |
折口慎一郎 | 53分 |
ノミネート作品
| 作品名 | 監督名 | 時間 |
|---|---|---|
| 『死ぬか生きるか』 | 村橋明郎 | 82分 |
| 『17クラブ』 | 森 翔太 | 22分 |
| 『僕らの存在を聴け』 | 白田悠太 | 56分 |
| 『朝飯前夜』 | 鹿野洋平 | 22分28秒 |
| 『キャンセル兄ちゃん』 | 三澤拓哉 | 24分 |
| 『無法の愛』 | 鈴木竜也 | 22分 |
| 『かぐやびより』 | 津村和比古 | 106分 |
| 『ジンジャーミルク』 | 今井ミカ | 59分17秒 |
| 『母の反抗期』 | 近江浩之 | 23分 |
| 『ヘルメットワルツ』 | 西村洋介 | 89分 |
| 『燃やす』 | 丘澤絢音 | 31分37秒 |
| 『一筆の冬』 | 矢野恭加 | 91分 |
| 『せせらぎ荘』 | 高山 凱 | 125分 |
審査員コメント
大賞『ジンジャーミルク』
審査員 大林千茱萸
タイトルが示す“ジンジャーミルク”のように、甘いが仄かに苦い、なめらかというよりはざらっとした舌触りが残る、魂の奥深いところに静かに沁みてゆく作品です。
映画は、2020年4月、コロナ禍で大学生活を送るろう者と聴者、4人の生徒の関係を追う構図。その内の1人が、自分がゲイであることに気付き、悩み、友人にカミングアウトすることで、4人の立ち位置やそれぞれの考え方が炙り出され、関係性に変化が起きてゆく。「ろう者/聴者」それぞれの「文化/言語」、その中においての「葛藤」、あるいは「仲間意識」、もしくは「受け入れられない」という拒絶、「伝わらない/伝えられない」もどかしさ、加えて「若さ」という何重ものレイヤーが重ねられる。
映画の根底にある視線が、そもそも人の在り方として、ナニが正解でナニが間違いなのかを問うのではなく、いま、彼ら、彼女らが、性別を超え、ろう者と聴者の枠をこえ、人としてどのようにいまを生きているのか、精一杯ひたむきに自問自答しながら生きている登場人物たちを丁寧に見詰めていることに感銘を受ける。観客はその視線に寄り添いながら、私たち自身も考える。映画に導かれながら「マジョリティ/マイノリティ」を超えて考えて観ることができる――が、ときおり「ろうの人って優しいよね」と、ドキッとする一言がサラッと入れ込まれていたり、手話の「好き」には友人には使わない、恋愛だけに使われる手話があること、「手話は日本語とは違う」こと――など、知らない世界を教えてくれる。観ることで、新たな知識や文化を共有させてくれる。カミングアウトする青年が主人公のようであるけれど、それすらも限定しないスタイルになっている。それは「描ききる」という確固たる強い製作意思がなければ作品として到底まとめきれないもので、ゆえに、本作はとても力のある作品でした。
心に残る素晴らしい場面が幾つもあります。ジンジャーミルクの美味しさを身体で、踊るように表現する場面には、思わずグッと引き込まれます。ことにエンディングに向かう夜、橋全景を捉えた画面の中を歩いてやってくる登場人物×遠くから向かってくる電車×通り過ぎる電車の横で言い争う場面には胸をかきむしられます。撮影も素晴らしく、セリフではなくカットバックの重なりで成り立っていくわけですが、聞こえるわけがない、声にならない「声が聞こえる瞬間」が、確実にソコに映っていました。大げさではなく、青春映画史の名場面のひとつであると確信できます。
映画は画で描かれるものですが、画と画の間=余白を丁寧に物語の流れに入れ込むことで、観終わってからも作品の余韻が長く続きますし、考える時間もくれる映画です。素晴らしい体験をどうもありがとうございました。大賞、おめでとう御座います!
審査員 柘植靖司
音のない世界―。ろう者と聴者、4人の若い男女間で起きる恋愛模様がもどかしく、切なく伝わってくる。今年の応募作品にはコロナ禍であることを扱った作品がより一層多くなり、作家やその作品が敏感にその時代を反映しているという意味でそれぞれにとても興味深く拝見ました。この作品の登場人物たちもコロナ禍で大学生活を送っています。緊急事態宣言下、授業はリモート、お互い直接会うことも叶わない。彼らのコミュニケーションはスマホとパソコンでの映像―。しかも、そこでの会話は手話で行われます。その多くがミディアム・ショットとバスト・ショットで構成され、スマホやパソコンに向かって意思を伝えようとする彼ら、彼女らが愛おしくなりました。無音のカット、その長さに独特のリズムがあり、見る者に登場人物の心の声を想像させ、引き付ける力を感じました。更に数少ないロング・ショットがそれを引き立てています。
人に好意を抱く気持ち、恋をしている感情は、ろう者も聴者も変わることはないわけですが、それを表現する形が異なる。手話というひとつの言語が独立して存在していることをこのコロナ禍を舞台に見事に表現していると思いました。そしてその表現に性差も感じない。高架下でのラスト・シーンはこのドラマの終わりとして見事であり、驚きでした。
『ジンジャーミルク』なるものを私は飲んだことはありませんが、きっと優しい気持ちになるだろうなと思わせました。
スタッフが聴者であるのが当然の撮影現場しか経験のない私からすると、この作品の制作にあたり、様々な困難があったのではと想像します。
最後にろう者である監督とともにこの作品に関わられた全てのスタッフに敬意を表します。
審査員 古厩智之
人と人が対峙する。瞬きは止まり、緊張感が溢れる。
そして「二人のあいだにあるもの」が目に見え始める。
好意、裏切り、憤り、もどかしさ…。
こんなに力に溢れたカットバックを初めて見た。「目に見えるコミュニケーション」だけで生きている、ろう者でもある監督ならではなのだろう。
「ろう」であること以上に、「人と人とのコミュニケーション」を信じているから今井ミカ監督のカットバックは唸りを上げる。「さぁ行くよ」「私を見て」「あなたを見るから」と。
そんなカットバックから解放され、ひとつのフレームに二人がおさまるクライマックス。
いや、決しておさまってはいない。「解決はない。でもこうやって生きていく」という生命力に溢れた叫びそのものだった。
大林千茱萸賞『無法の愛』
審査員 大林千茱萸
2022年度のうえだ城下町映画祭第20回自主制作映画コンテスト、応募数は過去最多153本にまで膨れ上がったが、まず、今回の応募作の中で、紛れもなく、いちばん“かっこいい”映画でした。音楽もかっこいい。最初の一音目から脳内が痺れ、映画に心地好く誘われてゆく。これほど“かっこいい”に特化した作品は珍しく、最後の最期まで失速を知らず、テンションが落ちないところも見事でした。サントラがあったら欲しいほどです。
実は今年の応募作には何作か、携帯サイズの作品がありました。映画は発明品なので進化してゆくもの。決して携帯の縦長サイズが悪いわけではないけれど、このアスペクト比は意外と人やモノゴトの動きに制約を与え、不自由ではある。他応募作でも画面作りに果敢に挑んでいる作品がいくつかあったが、どこか形式的で自由度が少なく、それが「発明」にまでたどり着いているのは『無法の愛』だけであった。縦長→横長のアスペクト比にトランスフォームするタイトルバックは閃きと輝きに溢れていて秀逸で、唸りながら何回も観てしまった。閉塞感と疾走感のせめぎ合いがすごいバランスで成り立っていました。
登場人物の男女は、いわゆるボニー&クライド風味。もしくは1973年テレンス・マリック監督の『バッドランズ/地獄の逃避行』的。ふたりの愛の形は常にバイオレンスにまみれていて、デートはすべて暴力と犯罪。ゆがんだ背景から産み落とされた男女の出逢いと別れと、また“違った形での出逢い”が描かれる。アニメーションとして「絵」で描くことで、実写では描ききれない、セリフだけでは説明できないことを、絵が補い合って融合させているのも素晴らしかった。
京王線の無差別殺人からインスパイアされたであろう、疲弊した世相。SNSの恐怖。感情なく淡々と語るニュースキャスター。「いま」が切り取られていて「いま」作っておく映画なんだなと腑に落ちる。
コトが済んだあとの、窓向こうの風景が、すごくいい。たぶんもう天国。ふたりに安らぎがあらんことを! 鈴木竜也監督27歳作品。ナニかスケールの大きい、得体の知れぬ作品を拵えてくれるのではとの期待と希望を込めて――僭越ながら大林千茱萸賞とさせて戴きました。コレすべて独りで作ったとは、なんて“かっこいい”んでしょう!!!
柘植靖司賞『僕らの存在を聴け』
審査員 柘植靖司
「上手いな~」と感心して見ました。特にカット・インされる映像の入れ方にリズムがあり、効果的で印象的でした。配役もよく、それぞれの役柄を的確に演じています。
とても演出力があり、全体的に破綻がなくドラマに惹き込まれていきます。
これは多分、この作品で表現したいことが監督の中で明確になっていて、揺るぎがなく、緻密に計算されているからだと思いました。そして、監督自身が実際に体験したことが礎になっていることが大きいと思います。普段、キャラクターを設定して人物造形をしていく時、その人物の履歴や映画の中では描かれないドラマを設定し、それを経て表現される映画の中で人物がどう動いていくのか組み立てていくのですが、この作品ではその人物造形が監督の中ですっかり出来上がっているのだと思いました。聞けば、本作品の前段ともいうべき作品を監督は制作していたとか…なるほど。その作品が大いに本作品に貢献したともいえるでしょう。しかし、この作品からだけでも監督の心からの『叫び』はしっかり聴こえました。
ただ、個人的な欲を言えば、上手く出来過ぎているがゆえに、あっと驚かさせられる何かがぶち込まれていてもいいのかな、とも思いました…何か判りませんが。
監督は自らゲイであることを表明し、LGBTQ+の活動をされているとのこと。この映画はその活動にもひとつの大きな役割を果されていると思います。LGBTQ+に纏わる世の中の理解度も10年、いや5年も経てば大きく変化するでしょう。その5年後、10年後に白田監督がどのような作品を撮られるのか、楽しみにして『柘植賞』をお送りいたします。
古厩智之賞『かぐやびより』
審査員 古厩智之
生きづらさを抱える人たちの作業と暮らしの場・さんわーくかぐや。そこの彼らのことが頭を離れない。
楽しいことがあると横揺れで踊る大王さま。
天才的な白菜や百合の絵を描くカホちゃん。
流しそうめんがたまるバケツの横で“たまりそうめん”をマイペースに楽しむ前田さん。
「愛してますよ」「結婚したいです」と愛に溢れたタクミさん。
悲しいことがあると速攻で泣いちゃうのに、やがて自立の道を歩き始めるリコちゃん。
みんなのお母さん代わりの園長、いい距離感の二枚目副園長…。
出演者みんなを好きになってしまう。そして人を好きになる自分自身をも好きになれる。
そんな奇跡のサイクルが起こる傑作ドキュメンタリー。感動しました。
実行委員会特別賞『走れ!走れ走れメロス』
副実行委員長 角田千広
映画祭の実行委員会というのは、映画製作のプロではないただの映画好きの集まりなので、「実行委員会特別賞」は、他の映画賞でいう「観客賞」に近いものかもしれません。
だから、見て「面白い!」というものが選ばれることが多いのですが、この作品も、見て素直に「面白かった」です。
昨年も、ドキュメンタリー作品の「YOKOSUKA 1953」が、実行委員会特別賞と大林千茱萸賞に選ばれたわけですが、特にドキュメントにこだわっているわけではありませんので、念のため。
仕方なく入ったような学校で、特にやりたいこともなかった生徒たちが、与えられた「演劇」という舞台のなかで、次第に成長しのめり込んでいく姿は、見ていて清々しかったです。
もちろん、指導の先生の力が大きかったのでしょうが、それ以上に「青春をぶつける」という、なかなか今時でない「熱気」が画面から伝わってきました。
最後の方は、少し指導の先生の話にシフトしてしまったのは、ちょっと勿体無い感じもしましたが。
ドキュメンタリーといえども、映像作品ですから、当然作り手の意志、「どの視点から」「どこをどう切り取って」「どうまとめるか」によって出来上がったものの印象はかなり違ってくると思います。
その点、この作品は、素材の良さも大きいですが、それに正面から向き合って「面白い」そして「熱気が伝わってくる」というドキュメントに仕上がっているのは、作者の力が大きいと思います。